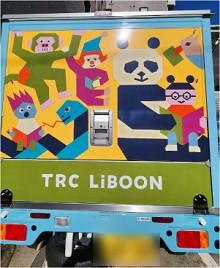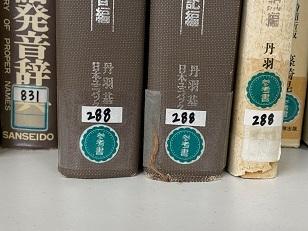TRCの典拠ファイルには8つの種類(「個人名」「団体名」「出版者」「件名」「学習件名」「シリーズ」「全集」「著作」)
があります。そのうち、私の所属する典拠チームで扱っているのは「個人名」と「団体名」。
この連載「典拠のはなし」という名前になっていますが、これは言葉どおり「典拠(ファイル)のはなし」ではなく、実は「(典拠チームで扱っている)典拠(ファイル)のはなし」なのでした。
典拠チームで扱う典拠ファイルは「個人名」と「団体名」。とはいえ、こちらのブログで話題にしているのはほとんど「個人名」ですね。典拠ファイルの件数も「個人名」が東洋人(日本人含む)西洋人合わせて140万件近いのに対し、団体名は31万件弱(2025年9月現在)とかなり少なめです。
なかなか注目されない「団体名」。不憫な気持ちになってきたところで「団体名」ならではの特長をあげていきたいと思います。
■同名異団体の識別
個人名は同名異人が多く悩みの種ですが、同じ名称の別団体というのも多くあります。
例えば「社会民主党」。
統一形:社会民主党 ←現行の政党
統一形:社会民主党(1901)※←かつてあった政党
現行の「社会民主党」は日本社会党が1996年1月に改称してこの名称になったものです。実は1901年に日本最初の社会主義政党として結成された「社会民主党」がありました(結成後2時間、2日など諸説あるもののすぐに廃止)。
この2つの団体を分けて検索できるように典拠ファイルではそれぞれ統一形を作成しています。
かっこ内※の「1901」は「標目限定語(創立・所在地等)」です。1件目の「社会民主党」との識別のために付与しています。
団体名の場合、団体の創立年、所在地、性格などを標目限定語として標目限定語として付与します。
標目限定語(付記)全般についてはこちらの記事をご覧下さい。
■異名同団体の識別
異なる形で出現した同一団体をまとめる仕組み(直接参照)は2種類あります。考え方によっては個人名よりも団体名の方が、この機能に助けられるケースが多いかもしれません。
1つは同じ団体に略称や愛称、別称があるケース。
統一形:図書館流通センター
参照形:TRC
このブログのタイトルが「TRCデータ部ログ」とある通り、社内でも自社のことをしばしば「TRC(ティーアールシー)」と呼んでいます。
責任表示が「TRC」となっている図書があれば「TRC」は記述形だったのですが、残念ながら?参照形です。(記述形と参照形についてはこちらの記事が詳しいです)
もうひとつは団体の下部組織があるケース。
統一形:図書館流通センター
記述形:「TRC MARC人名典拠録」編集部
もしも下部組織が「図書館流通センターTRC MARC人名典拠録編集部」というように、上部組織の名称からはじまっていれば、図書館流通センターが著した図書を探したときに、その中の一部署が著した図書を発見することができます。しかし、そうではないケースが多々あり、そうした場合、図書の発見には典拠ファイルが不可欠です。
これらは団体名典拠ならではの機能です。
他にも団体間、団体個人間の関連など団体名には使いこなしていただきたい機能がたくさんあります。
そちらはまた、改めてブログの記事で扱っていきたいと思います。