TRC MARCニュース第28号発行しました
TRC MARCの最新情報をお届けする「TRC MARCニュース」(不定期刊)の第28号を、8月29日に発行しました。
内容は、
1.雑誌データ
2.ベルグループの新設
の2点です。
TOOLi(図書館専用ポータルサイト)でもご覧いただけます。
TRC MARCの最新情報をお届けする「TRC MARCニュース」(不定期刊)の第28号を、8月29日に発行しました。
内容は、
1.雑誌データ
2.ベルグループの新設
の2点です。
TOOLi(図書館専用ポータルサイト)でもご覧いただけます。
先日、学生時代の友人宅へ遊びに行った時のこと。その家のクーラーも壊れたというこの夏の猛暑が話題になると、友人がすかさず「もしかして、クーラー使ってないでしょ?」 なぜわかったのだろう…。我が家のエアコン(←あるにはある。一応)のコンセントは抜かれたきり、1mmも動かないまま幾星霜なことが…。
別に「地球温暖化云々」というようなポジティヴなポリシーがあるわけではなく、風の吹き抜ける冷房いらずの家で育ったので、「エアコンのある生活」というのがよくわからないだけなのです。暑い暑いと大汗かいてる間にスイッチ入れようよという、ただそれだけのことでも、子どもの頃からの習慣というのは侮れません。「エアコンがある」という大前提にさえ思い至らないまま夏が過ぎていってしまうのです。
以前、大谷が紹介していましたが、ここデータ部は冷房の設定温度が高め。期せずして職場でも家でもかなり地球にやさしい生活を送ることになっております。こんなゆる~いエコもありですよね。(それにしても、つくづく暑い8月だった…)
酷暑も今度こそ終わったか?終わったわよね?というここ数日ですが、先週・今週、こちらの部署では、早くも編み物、しかも↓のような秋・冬ニットの本を何冊も目にしました。
ためしに 件名:編物 で探してみると、昨日発行の「週刊新刊全点案内 1534号」では23件の掲載が(その前しばらくは0~数件でした)。鎖編みから先に進めない編み物コンプレックスの私にはよくわからないのですが、世の中ではそろそろ、編み物のシーズンインなのでしょうか。
今からデザインを選んで毛糸を揃えて、秋の夜長に編み進める、というのも贅沢な時間の使い方ですね。
本日「月刊新着AV案内no.17(9月号)」を発行しました。
掲載点数は1027件。内訳はDVD:281点、ビデオ:2点、CD:739点、カセットテープ:5点です。

今回の表紙画像を見て「あ~ん」と思った私は、実はお裁縫が趣味なんですが、チビ怪獣(1才7ヶ月♂)のせいで、ミシンとはとんとご無沙汰です。
裁縫道具はチビに危ないものばかりだし、チビのせいで裁縫道具も危ない(壊される危険性大)。
眠ってる間にアイロンをかけてると、いつのまにか起きだしてコードを引っ張ってたりします。
怖いんです・・・。
さて今号の月刊新着AV案内について、今回は、山老のお隣のAV岩瀬よりコメント。
岩瀬>今回の映像資料には、鉄道ものが20件余り掲載されています。(「特急はくたか」「阪急電車大全集」等々)これが結構担当者泣かせなんです。
件名をつけるため、その路線が何県を走っているのか地図とにらめっこして調べますし、駅名のヨミもクセモノ。同じ名前でも地名と駅名ではヨミが違うこともありますし。
電車は旅気分も盛り上がります。広い車窓や車内販売のワゴン、倒せるシートやフットレスト、駅弁など、まつわるものがまた楽しい。でもMARCとなると、眉間にしわをこさえることもあるのです。
本日、「週刊新刊全点案内」1534号を発行しました。
掲載件数は1518件です。
こんにちは。 新刊目録 中村です。8月最終週、学生の皆さんは夏休みもフィナーレを迎え、宿題に追われる日々でしょうか(…○○年前の自分の姿か)。
夏休みといえば里帰り、両親とも親戚の大半は同じ町内に住む私にとって、結婚してはじめてできた習慣です。義父母はまだしも九十歳を越えた義祖父母と何を話したらよいものやら。曾孫をダシに、健康や庭の木々をネタに…気づけば過ぎていくのですが、毎回ちょっと悩むものでした。
そんな人が他にもいるのか、こんな本が出ていました。
年老いた両親への話しかけ方・聞き方を、用例豊富に紹介しています。体の具合がわるいと愚痴が止まらないとき(苦笑)、悪口ばかりが続くときなど、困った時の一問一答もあり。会話術というより、どうやって話をひきだすか「聞きだす術」に重点が置かれています。
こんな一冊も
「聞く」という行為は、「相手が満足する」ことに直結している! わかりやすい文体で「聞く力」の大切さ、「聞く」センスの磨き方を説いています。わが家はみんな話好き+マイペース=人の話を聞かない、のでちょっぴり反省+とーっても勉強になりました。
~内容/目次 その3~
目次情報ファイルは文字通り、図書の目次ページのデータベースです。作成対象は、一般書のうち研究者向けと大学生向けの図書、それから児童書ノンフィクションです。一般書は2005年から、児童書は2006年から作成していて、2007.8.10現在9900件余りの累積があります。2007年は、
目次情報対象冊数 2,844冊
(内訳) 一般書 2,032冊
児童書 812冊
を作成しています。
目次情報ファイルは内容細目ファイルと違い、第1階層、第2階層の2階層の構造をとっており、目次ページの大きい項目から順に入力しています。
こんな感じです。
児童書ノンフィクションは目次にあるものすべてを入力しています。
こちら
目次情報ファイル作成では、内容細目ファイルとはまた違った悩みが出てきます。たとえば大学生向けの図書などで公式や数式が章のタイトルにでてくることがあります。その式が入力できないときはヨミで入力しますが、その正しい読み方への長い道のりが待っています。また、児童書ではいろいろな記号がついていることが多く、できるだけそれに近い記号で入力して少しでも雰囲気がわかるようにしています。
週刊新刊全点案内の右側の欄の利用対象の下に赤字で〔目次情報〕と表示されていれば目次情報ファイルがあります。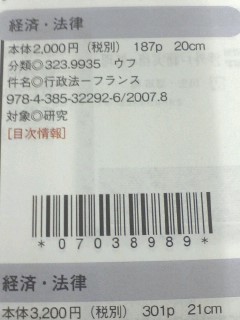
bk1では、こちらの 目次へ をクリックしてご覧下さい。
この図書はどんな内容なのか、どういうことについて書かれているのかといったことがすぐにわかり、より専門的な主題がつかめると思います。
また、内容細目ファイルと同様bk1ではキーワードで検索できます。○○ってどうやってできているの?と不思議に思ったり、何かを調べたいときなど、どの本にそれが載っているのか探し出すことができます。
(<2015.4.6追記>現在bk1のサービスは終了しており、TRCブックポータルでのご案内になります。TRCブックポータルでは内容細目は検索できますが、目次情報での検索は対象外となっております。)
目次情報ファイル作成からまだ2年半ですが、内容細目ファイルと同様お役に立てると思いますのでぜひご活用下さい。
次回は週刊新刊全点案内に掲載しない新刊書MARCと、部署で大活躍のスキャナの秘密に迫ります。
こんにちは。先日のエントリー(「夏休みのアルバム」)に載せたひまわりの写真が、周りの人たち(といっても2人だけですが)に好評で、喜んでいる望月です。
とはいえ、携帯のカメラで通りすがりにパシャッと撮っただけなので、「いい写真ですね」なんて言われるとちょっと困ってしまうのでした。たまたまいい感じに取れちゃっただけなのです、ほんとのとこ。
さて、2枚目の写真のゴーヤーの話。
写真で見ると大きく見えるようですが、実はこのゴーヤー、手のひらサイズです。
それを3つもらったので、2つはゴーヤー・チャンプルーに、もう一つは野菜炒めに混ぜて食べました。
小さいからそんなに苦くないかと思ったら、しっかり苦くて、おいしくいただきました。
しかし、このゴーヤーを育てた祖父は「ゴーヤー」という名前が覚えられません。
「あのえーと、ゴ、ゴキブリじゃなくてなんだっけ?」
ゴキブリじゃないよ、ゴーヤーだよ、と何度言っても「ゴ」で止まってしまうのです。
たしかに、ゴーヤーが一般的になったのはここ最近のこと。祖父の耳になじみがなくてもしょうがないのかもしれません。スーパーでも、少し前までは「にがうり」と表示されていた記憶もありますし。
そこで、TRC MARCを検索。ゴーヤー料理や栽培の仕方の本をピックアップしてみたら面白い結果になりました。
「ゴーヤー(にがうり)料理60選」 1984.5
「ゴーヤーブック 体にいい苦瓜料理」 1998.2
この2冊はどちらも沖縄県で発行されたもの。地元の言葉なのでゴーヤーがタイトルに入っています。
「やさいを育てて食べよう 1 にがうり」 2003.2
「ニガウリ(ゴーヤー)の絵本」 2003.3
「育てよう!食べよう!野菜づくりの本 4 トマト・なす・ゴーヤ」 2003.4
2003年発行のこれらの本は、「にがうり」だけだったり、かっこで「ゴーヤー」と補われていたり、「ゴーヤー」だけだったり、書き方もいろいろです。ゴーヤーという名前が広まりつつある頃だったのかしらん、と推測してみたり。
時代によって、物の名前も変わっていく。そんな一例でした。
こんにちは、図書館蔵書 小松です。
子どもたちの夏休みもそろそろ終りが見え始めたところで、以前みつけたおみやげの話を・・・と思っていたら・・・みんな考えることは同じとみえて、先をこされてしまいました・・・。
めげずに、Part2として九州は太宰府限定のおみやげと絵本のご紹介です。
福岡県太宰府市といえばもちろん太宰府天満宮、政庁跡(都府楼)、観世音寺・・・そして2005年Openの九州国立博物館です。
子どものころから博物館によく遊びに行きました。展示ももちろん楽しいのですが、博物館に付随するミュージアムグッズやお食事も見逃せない楽しみでした。今みたいな真夏にはひんやりした館内も極楽でした。
その楽しみのひとつ、ミュージアムグッズ。最近メジャーになってどこの美術館博物館にもありますが、各地の国立博物館も流行のかなり早い時点から、ずいぶん色々な凝ったグッズを出してきました。子どものころ遊びに行った上野の東京国立博物館のミュージアムショップなんて宝の山。どうしても尾形光琳の八橋蒔絵硯箱のレプリカ(たしか何十<百?>万もした)が欲しかった博物館好きのヘンな子どもだった私・・・。実は今も欲しいです・・・ヘンな大人。
気を取り直して、
九州国立博物館はミュージアムグッズに加えて、絵本も出版しています。
8/31まで「NTT西日本スペシャル 絵本カーニバルin Fukuoka2007 きゅーはくの絵本であそぼう!」という特別イベントも開催されているのだそうです。
「まいごのぴーちゃん きゅーはくの絵本」
九州国立博物館企画・編集
フレーベル館 (2005.10)
じろじろぞろぞろ きゅーはくの絵本 2
九州国立博物館企画・編集
フレーベル館 (2005.10)
「まいごのぴーちゃん」は、色絵皿の模様から生まれた小鳥のぴーちゃんが、花鳥文様の世界に紛れこんで遊ぶうちにまいご(!)になって、アジア各地のさまざまな工芸品を尋ねる話。どのページもどのページも美術品の模様の一部分なので、ストーリーのかわいらしさもさりながら、図像がとても綺麗。
「じろじろぞろぞろ」は南蛮屏風を、絵巻物などで流行っている絵解き(えとき)風に見て行くもの、現代から見るとちょっと不気味な人物像と、おかしみのある文章が一体になって、題名の雰囲気とも似た不思議な味があります。
このシリーズは美術品の中に入り込んで、ストーリーを展開していくものですが、やはり長い間伝わってきたものには、こうして一部分切り出した、部分部分にも人をひきつける力があるんだなぁ、とちょっと感動します。
以下、
エイサー! ハーリー(きゅーはくの絵本 3)
はらのなかのはらっぱで(きゅーはくの絵本 4)
ぞくぞく ぞぞぞ(きゅーはくの絵本 5)
と続刊(こちらは未見)があります。
そして問題のおみやげはこちら・・・
本日、「週刊新刊全点案内」1533号を発行しました。
掲載件数は1188件です。
厳しい暑さが続いていますが、お盆が過ぎれば、強い日差しの中にも少しずつ秋の色を感じます。
この時期、子どものころの「夏休みの終わりが近づく」さびしさが、なぜか今でも胸によみがえります。
そういえば、私がはじめて町の図書館に行ったのは夏休みの宿題がきっかけでした。「学校の図書室より本がいっぱいあるよ!」という友だちの誘いにのり自転車で30分。きーんと冷えた明るい室内には、本当にいろいろな本がぎっしり並んでいて、その一瞬、宿題のことは頭から消えました。
*こんな本がありました*
各都道府県別に、旅のおみやげにおすすめの名物名産品を紹介。ご当地キティや地域限定お菓子などもおさえています。中には必見の「珍品」もありますよ。
おみやげ品というのは地域の歴史や特色を反映したもの。苦手な地理の知識も、これなら頭に入るかもしれません。お父さんお母さんのふるさとの話でもりあがったり、地元の「おみやげ」に対し「もっといいものがあるのに!」とツッコミを入れるのもまたよし。楽しみ方いろいろです。
じつは私もついつい旅先で「ご当地キティ」を買ってしまうひとり。この本も前々から気になっています。見るとどれも欲しくなってしまいそう。
また「なぜこんなみやげを買ってしまったのだろう」と後悔しがちな方(それも自分か…)にはこちら。
(※下2件は既刊です)
~内容/目次 その2~
内容細目ファイルは収録作品のデータベースです。一般書・児童書の総合全集、個人全集、著作集、作品集、論文集、講演集、対談集、随筆集などに含まれる独立した著作を対象としており、2007.7.23現在11万件を超える累積があります。2007年だけで見ると、
内容細目対象冊数 3,171冊
収録タイトル件数 45,350件
著者名件数 27,024件
となります。2006年は1年で5400冊ほどでしたが、2007年はおそらくその数を超えるでしょう。
この数字を見ると、1冊の平均収録タイトル数は15タイトルほどですが、そのタイトル数の多さと作業の大変さは一致しないことのほうが多いのです。1タイトルごとに著者がいればその典拠作業は典拠の部署が行いますが、私たち内容/目次の部署で大変なのはタイトルのヨミがすぐにはわからないときです。理数系などで多く出てくる専門用語、あまりメジャーではない外国語などのときはありとあらゆる辞典類にあたったり、語学に強い人に尋ねたり、でかなりの時間を要します。もちろん出版社への確認もあります。そのうえ、旧字が多くなるとまたかなりの時間がかかることに…。
さて、1つのMARCの内容細目ファイルで収録できるタイトル数には限りがあります。その制限は499タイトル。ですので、それ以上のタイトル数がある図書では残念ながら収録できない作品が出てきます。499タイトル以上収録してある図書はそんなにありませんが、それでも民話集などはこの制限にかかってくるものがあります。タイトル数の多さは作業の大変さに一致しない、と書きましたが、ここまで多いと身構えます。
こちらは、最後の499番目のタグに ほか344編 と入力しました。
内容/目次の部署にはMARC作成の流れの中では比較的早く図書がやってきますので、ヨミの調査や著者典拠の多いものなどが発生するとかなりスケジュールがきつくなります。あらかじめわかっていれば図書をいち早く流してもらえますがやはり期限がありますので、予告があるとメンバー全員緊張してその到着を待つことになります。
週刊新刊全点案内の右側の欄の利用対象の下に赤字で〔内容細目〕と表示されていれば内容細目ファイルがあります。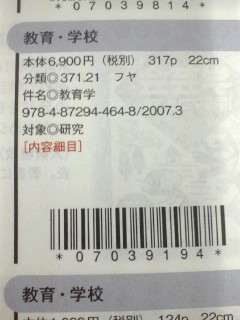
bk1ではキーワードで検索できます。
こちら
これはメッセージ集ですが、収録されている人たちの名前からでも検索できます。収録作品一覧へ をクリックすれば見ることができます。
お役に立てると思いますのでぜひご活用下さい。
次回は目次情報ファイルについてご紹介する予定です。
お久しぶりでございます。データ部ログでございます。
ただいま夏季休業中ではございますが、のこのこと会社に出てきて、こまこまと仕事をしておりますので、合間を見て更新してみました。
今年の夏休みは、実家でゴロゴロする、お墓参りをする、祖父宅に遊びに行く、といういかにも夏休みらしい過ごし方で過ごしました。
暑い中、扇風機の風を浴びながらのんびりする贅沢。
たっぷり味わってきたので、また来週から元気に働きましょう!
先週の MARC MANIAX 目録では、目録の情報源について、とりあげました。
図書のカヴァーの扱いについて、少し補足いたします。
昔の図書館では、破損や紛失のおそれのあるカヴァーは最初から外してしまってラベルを貼っていたと思います。あわせて目録も図書本体の情報をもとに作成する。国立国会図書館でもカヴァーは廃棄しているというお話が、以前新聞記事で紹介されていました(2004年12月18日朝日新聞)。
TRC MARCの作成においても、長らく「カヴァーは無視、本体のみ情報源」を原則(一部例外措置あり)としていました。
しかし皆さんご存知のように、現在、多くの公共図書館ではカヴァーの上からブックコートをかけています。文芸書やビジネス書など一般の方に広く読まれる分野の書籍は「本体はスッピン、カヴァーでお化粧」が一般的なスタイル。(ただし全面ブックコートにはお金と手間と時間が少なからずかかっていることをお忘れなく)
すると今度は本体の背と表紙がもう見えません。カヴァーと本体でタイトル表示が違っていたり、カヴァーにしかない責任表示、シリーズ名があったりで、目録作成上こまごまと困ることがあります。書誌が図書の見た目と違ってわかりにくいというご指摘を受けることもありました。そう、化粧を落とすと別人です…。そのため、2005年より、カヴァーも主たる情報源のひとつとすることにいたしました。
* * * * *
さて、お盆の時期は取次の書籍配送がお休みになります。出版社の方も休暇をとるのでしょう、新刊見本の入荷も少なくなって来ました。来週一週間、TRCは夏季休業とさせていただきますので、データ部の業務とこのブログの更新もお休みです。
明日はMARC MANIAX 目録の第2回。その次は8/20(月)から再開となります。またよろしくお付き合いください。
こんにちは、新刊目録 藤澤です。
私事ですが、私の父は退職後、近所の大学の実験室でパート勤務をしています。普段の仕事は、掃除や学生実験の準備などとのこと。楽しそうに通っているのでよかったな、と思っていたのですが、先日、意外な出来事がありました。
突然「見ろ」と向けられたパソコンの画面。そこには、本のタイトルやシリーズ名、巻次、著者、出版者がセルに収まったエクセルシートが…。どうも、仕事の余った時間で実験室の教科書や科学読み物を整理しようと思い立ったらしく、全ての本のデータをまずは打ち込んでみたのだそうです。
全集とシリーズが一緒になっていたり、項目の見出し名が違っていたり(シリーズ名をサブタイトルと命名etc.)と、完全に自分ルールで作ったファイルなのですが、これもやっぱり「目録」でしょう。
父はさらにこれをアルファベットで独自に分類し、色シールを付けて並べたいとのこと(数字をわざわざ読むよりも一目瞭然で良いのだとか)。「父さんが辞めたあと、後任が困るよ」とNDC(日本十進分類法)も紹介したのですがお気に召さないようで、今は鋭意分類中のようです。
父は、ここ数十年図書館には行ったことがないはず。私の仕事も会社名以外は知らないような人なのですが、それでも独力で「目録」を作り、本を並べようとしている…。人を整理・分類に駆り立てずにはおかない本の魔力を思わされた出来事でした。(そして、私の没入癖と独善・頑固さも父譲りか…と再確認したり)
先週からスタートしましたMARC MANIAX目録では、「簡単な目録を作ろう」というテーマで、目録作成のポイントをお伝えしていく予定です。ブログの限られたスペースの中では教科書のようにきっちりとまとめるわけにはいきませんが、父のような人にも何がしかのヒントが得られるよう、ポイントを絞ってざっくりとご説明できたらなと思います。
本日、「週刊新刊全点案内」1532号を発行しました。
掲載件数は1307件です。
先月にひきつづき、8月の表紙は夏まっさかり。
なんとなく縁側で楽しみたいアイテムたち…。

*こんな本がありました*
広島・長崎の原爆投下日、終戦記念日等、痛ましい戦争の記憶がよみがえり、平和への思いを新たにする8月。
この季節は、戦争をテーマにした本も多く目にします。
TRC MARC累積データをみても、特に太平洋戦争関係の本<件名標目: 太平洋戦争(1941~1945)>の刊行は例年、7.8月に集中しています。
1532号掲載分ではこんな本がありました。
戦争の記憶をもたない若い世代は、自分の先祖が戦争の時代を生きたことを忘れがちです。
でもこの本には、若者がその事実と真摯に向き合う姿が描かれています。
(また、著者が自衛隊員に憧れ、見事陸自の彼氏を見つけるといったような、若い女性らしいほほえましいエピソードも書いてありました)
もう一冊は、第二次世界大戦後の「日本軍山西省残留問題」を追ったドキュメンタリー。
映画「蟻の兵隊」 が、本になりました。
映画では伝えきれなかった真相に迫ります。
日々、たくさんの戦争をテーマにした新刊を見ていると、戦争はまだ終わっていないのだ、と思い知らされます。
~内容/目次 その1~
こんにちは。これから4回にわたって内容/目次の仕事内容をご紹介したいと思います。内容/目次の部署で作成しているのは、内容細目ファイル、目次情報ファイル、そして週刊新刊全点案内(以下、新刊案内)に掲載しない新刊書MARCなどです。
あの短篇はどの本に収録されているんだろう? このあいだ見た芝居の原作はどの本に入っているんだろう? と思ったことはありませんか? そこでお役に立てるのが内容細目ファイルです。また、「現代のドイツ経済の歴史」という本にはどういう内容が書かれているのだろう、というときに便利なのが目次情報ファイルです。
簡単にその対象となるものをご紹介しましょう。
内容細目ファイルは、小説集はもちろん、論文集、インタビュー集など独立した作品が収録されている図書を対象に作成します。
目次情報ファイルは、研究者向けと大学生向けの図書、それから児童書ノンフィクションが対象です。
新刊案内に掲載しない新刊書とは、図書館での利用に適さない書き込み式、音が鳴る絵本、楽譜、それからヌード写真集などですが、それらもきちんとMARCを作成します。
なんとなく感じはつかんでいただけたでしょうか。
さて、以前ご紹介したスキャナですが、そのスキャナが活躍するのがまさしく私たちの部署です。スキャン作業はその後の入力のためにきれいな画像が求められますので、暗幕を使用し、外からの光や室内の蛍光灯の明かりが直接入らないようにしています。ということは、空調もさえぎられ、かなりの暑さ...。当番になるとちょっと嫌ですね。冬は冬でこれまた寒いのですけれど。
次回は、内容細目ファイルの作成現場へご案内する予定です。
本日は、『週刊新刊全点案内』の中にある、既刊本を紹介するコーナー「書評に載った本」、
およびTRC MARCの中の書評情報についてご紹介します。
「このあいだの○○新聞に載っていたという本を探したい」「購入の参考にしたい」というご要望にお応えするべく「○日の○○新聞に掲載された」という情報をMARC上に持たせています。
まず、担当者が実際に新聞をめくり、書評欄をチェック。
対象としているのは「朝日新聞」「産経新聞」「日本経済新聞」「毎日新聞」「読売新聞」「中日新聞・東京新聞」の6種7紙です。
書評欄はたいてい日曜日にあるので新聞めくりは月曜日がピーク。
書評欄以外でも本の話題が載ることがありますので日曜日以外の新聞も目を皿にして探します。
手を黒くしながらの地道な手作業です。
新聞チェックが終わったら、該当する本のMARCを検索し、書評情報-新聞名と掲載日-を入力。
書評に取り上げられた本は既に発売されていることがほとんどですから、いちど完成したMARCを呼び出して、追加情報として入力することになります。
完成MARCに手を入れるのは緊張します。
しかも、月曜日がお休みの週は火曜日に大急ぎで処理。少々冷や汗ものです。
392$A01 朝日新聞
392$D01 2007/07/29 ←書評掲載日
392$G01 1532 ←「書評に載った本」に掲載する新刊案内号数
この書評情報をもとに、新刊案内のページを作成します。
「書評に載った本」のコーナーで紹介するのは、誌面の都合があるため「はじめて書評にとりあげられたもの」のみとしています。同じ本があちこち複数の新聞に紹介されることがありますが、そのたびに何度も登場することはありません。
しかし書評情報は複数入力しますのでMARC上には存在します。
たとえばこちらリリー・フランキーさんの「東京タワー」。さすがにたくさん付いています。
TRCが図書館向けに提供しているオンラインサービス「TOOLi」では、新聞名および掲載日から検索できます。
ちなみに、2007年8月現在で最多登場記録は、綿矢りささん「夢を与える」の計8回。
パーフェクトを達成した本、つまり対象新聞全紙を制覇したのは、いしいしんじさんの「みずうみ」と富岡多惠子さんの「湖の南」となっています。
(〈みずうみ〉の語をタイトルに入れると評判のベストセラーになる…ってウソです)
今日から8月。日差しがすっかり夏らしくなりましたね。
さて、真夏のデータ部。
ヒンヤリしたオフィスの中で仕事をしているのだろう、と想像されているかもしれませんが
実は社内他部署のフロアより少し気温が高めです。
どこのオフィスでもありがちな「冷房の風が直撃する席とまったく当たらない席ができてしまう」問題。
ほとんど1日中自分の席に座って仕事をしているので逃げ場がありません。かなり切実です。地球にやさしいかどうか以前に、寒がりの人の健康が第一。かといって暑くてボーッとなっては仕事に集中できず。かくしてエアコンの温度設定をめぐりはげしい攻防が…いえ、こまめに調節するよう皆で心がけています。暑がりの人は涼しい服装、冷たい飲み物、扇子やうちわ等で対応です。
結果、営業など他部署の人が来ると「なんだか暑い」。このあいだはプリンタの修理に来てくださったサービスマンさんが、気づくと汗だくで作業していました。気がきかなくて申し訳ありません。社外の方がいらしたときは、いつもより少し低めにしておこうと思いました。
パソコンやプリンタなどデリケートな機器がたくさんあるので本当は暑いとよくないのかもしれませんが、データ部はまだまだ人間さま優先。プリンタから出た校正リストもアツアツです。
そんなわけで、休日に買い物や食事に行き、予想外の寒さで夏カゼをひいたことがある私です。

エアコン操作パネルの前ではさまざまな駆け引きが…。